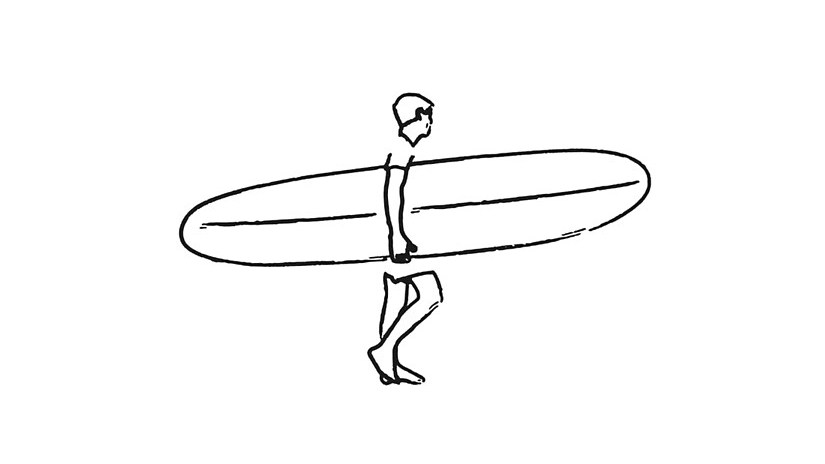ニューロダイバーシティと精神科
2024年12月1日付けで、宮崎大学医学部臨床神経科学講座精神医学分野の第四代目教授を拝命しました、平野羊嗣と申します。当教室は、1977年に初代教授の池田輝親先生(専門:神経生理学)のもと開設され、二代目教授の三山吉夫先生(専門:老年精神医学・神経病理学)、三代目教授の石田康先生(専門:老年精神医学・行動神経薬理学)の指導のもと発展を遂げてまいりました。この脈々と続く歴史ある教室の舵を取る責任の重さを感じております。
ところで皆さんは、ニューロダイバーシティ(Neurodiversity)という言葉をご存知でしょうか?Neuro(脳神経)とDiversity(多様性)を組み合わせた造語で、脳に関する様々な差異を「多様性」や「多様な個性」として捉え、その多様性を排除するのではなく、社会に包摂して活かしていこうという考え方です。
我々の社会は、異なる考え方や得意不得意がある多様な人間が集まり、パズルのようにお互いが補い合いながら構成されています。特に医療現場は、多種多様な人間と職種が力を合わせながら、あらゆる病気と闘っています。チームワークは勿論のこと、ニューロダイバーシティを重んじる精神が欠かせません。
一方で、精神疾患をニューロダイバーシティの最たるものと捉えると、人の心と脳を治療し、その病態解明を目指す精神科においては、ニューロダイバーシティの重要性は増すばかりです。革新的な発見や医療技術の進歩にも、ニューロダイバーシティは欠かせません。少し尖った能力や、常識を超えた発想の持ち主が、大きなブレークスルーをもたらすことが多々あります。
精神科医になるために必要な資質とはなんですか?とよく学生や研修医から質問されます。明確な答えはありませんが、あえて言うなら『相手(患者さん)に寄り添い、傾聴できること』だと思います。精神科には色んな技法や治療法はありますが、その根幹は『支持的な傾聴』ではないでしょうか。逆にいえば、その素養さえあれば、多少の得意不得意があっても、しっかりとした指導環境のもとでトレーニングを積めば、いい精神科医になれます。その点、当科では、優れた精神科医になるための指導環境を整えています。
臨床はもちろんのこと、研究も大学の大事なミッションの一つです。特に視覚化できる明確なバイオマーカーのない精神疾患においてはなおさら重要です。私もそうでしたが、多くの患者さんを治療する中で、精神医学を突き詰めていくと、自ずと『精神疾患の病態を解明したい』というモチベーションも出てきます。当科では、優れた精神科医の育成に加え、世界レベルで活躍できる研究者の育成にも全力で取り組んでいます。
宮崎大学精神科は、自由闊達な気風と多様性を大切にし、臨床・教育・研究に取り組んでいます。その多様性に富んだパズルをお互いが埋めながら、チームで患者さんを支え、そして精神疾患の謎に迫ることが我々のミッションです
心と脳、そしてニューロダイバーシティに興味がある方は、ぜひ当科の門を叩いてみて下さい。いつでもWelcomeです!
教授 平野 羊嗣
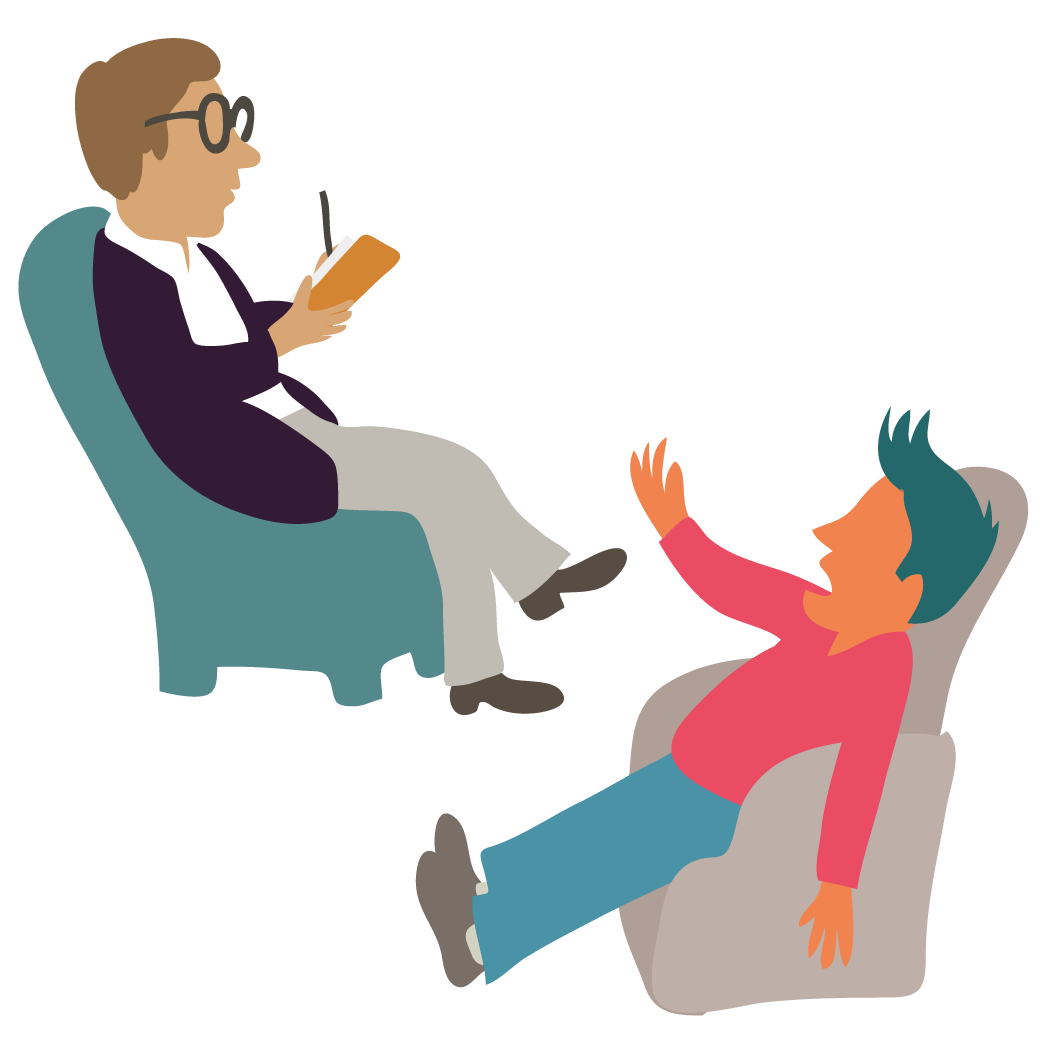
略歴
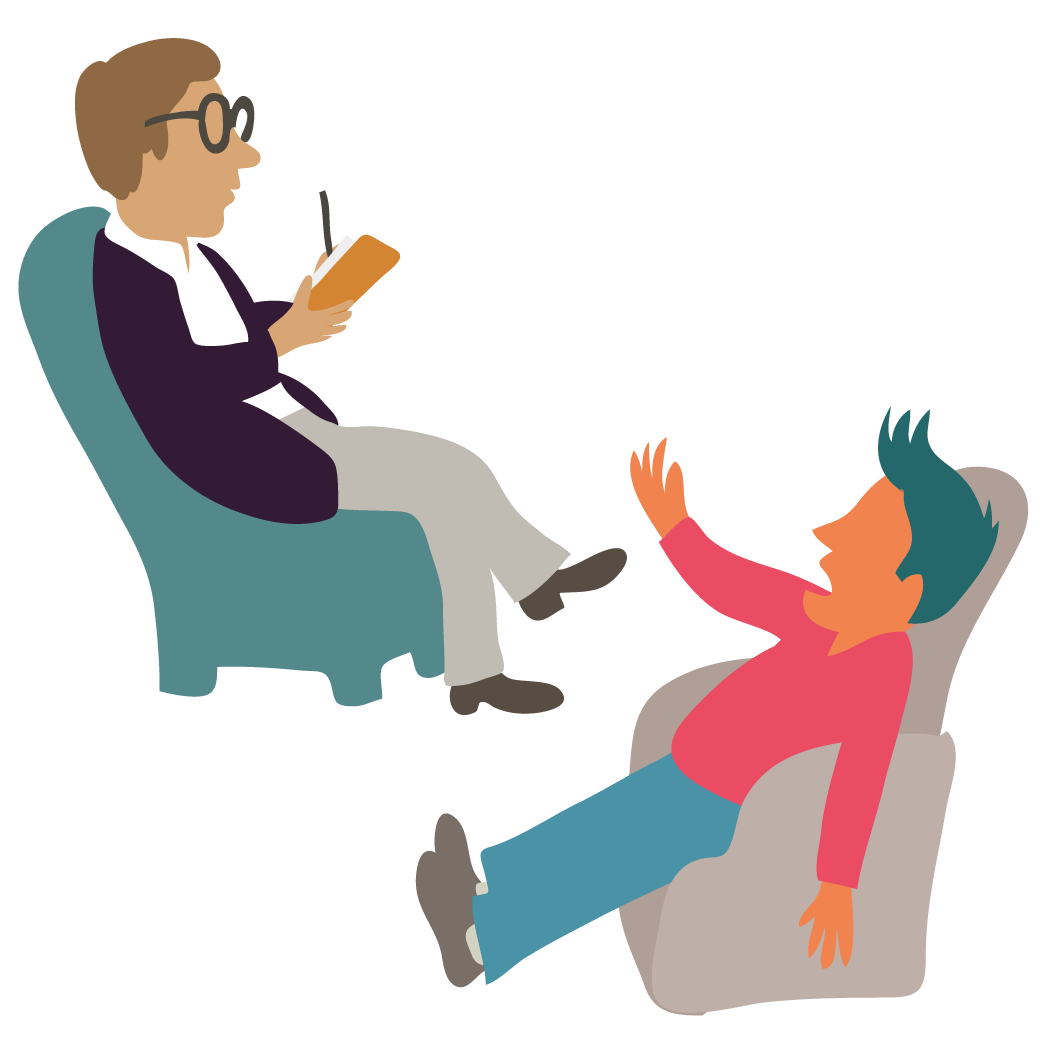
| 2000年03月 宮崎医科大学医学部卒業 |
|---|
| 2000年05月 国立病院機構九州医療センター・精神神経科・研修医 |
| 2001年04月 九州大学病院・精神科神経科・研修医 |
| 2002年04月 福岡県立精神医療センター・レジデント |
| 2004年04月 九州大学大学院医学研究院・精神病態医学・院生 |
| 2007年12月 九州大学大学院医学研究院・精神病態医学・助教 |
| 2008年04月 九州大学大学院医学研究院・精神病態医学・特任助教 |
| 2011年03月 Harvard Medical School・リサーチフェロー |
| 2014年03月 Harvard Medical School・講師 |
| 2014年04月 九州大学大学院医学研究院・精神病態医学・助教 |
| 2020年07月 九州大学大学院医学研究院・精神病態医学・講師 |
| 2022年12月 宮崎大学 臨床神経科学講座 精神医学分野・准教授 |
| 2024年12月 宮崎大学 臨床神経科学講座 精神医学分野・教授 |
| 現在に至る |